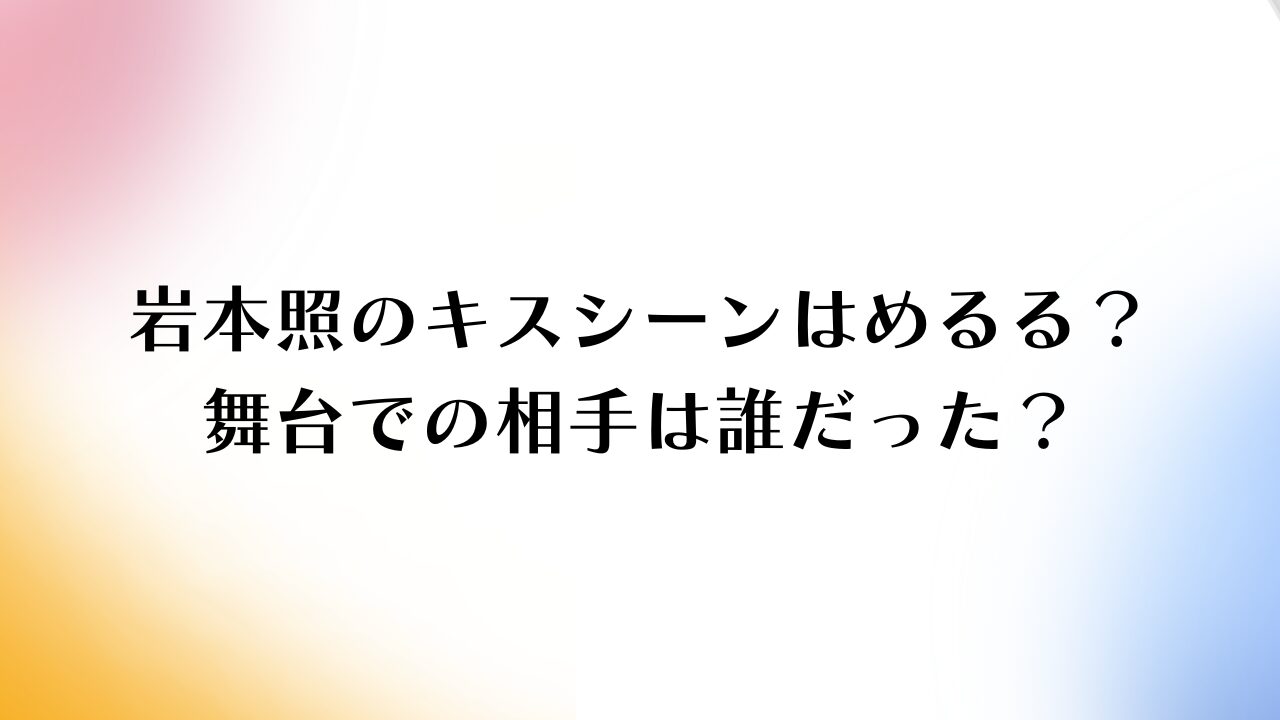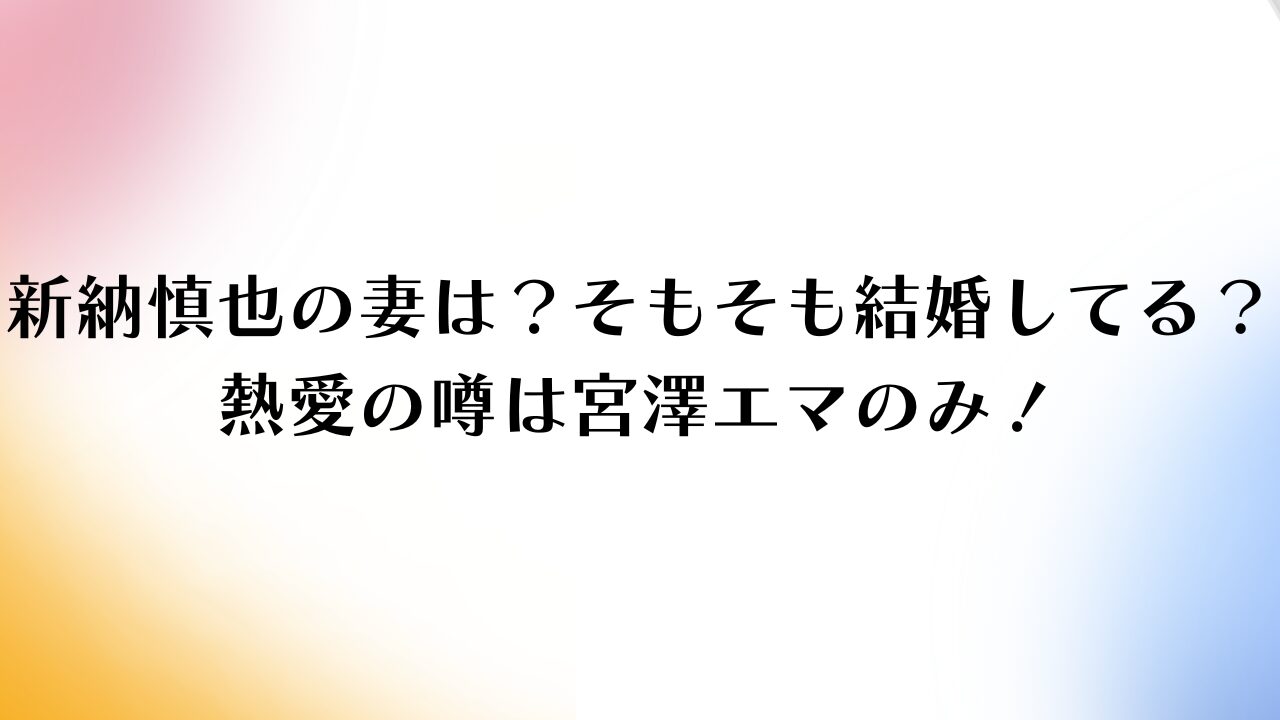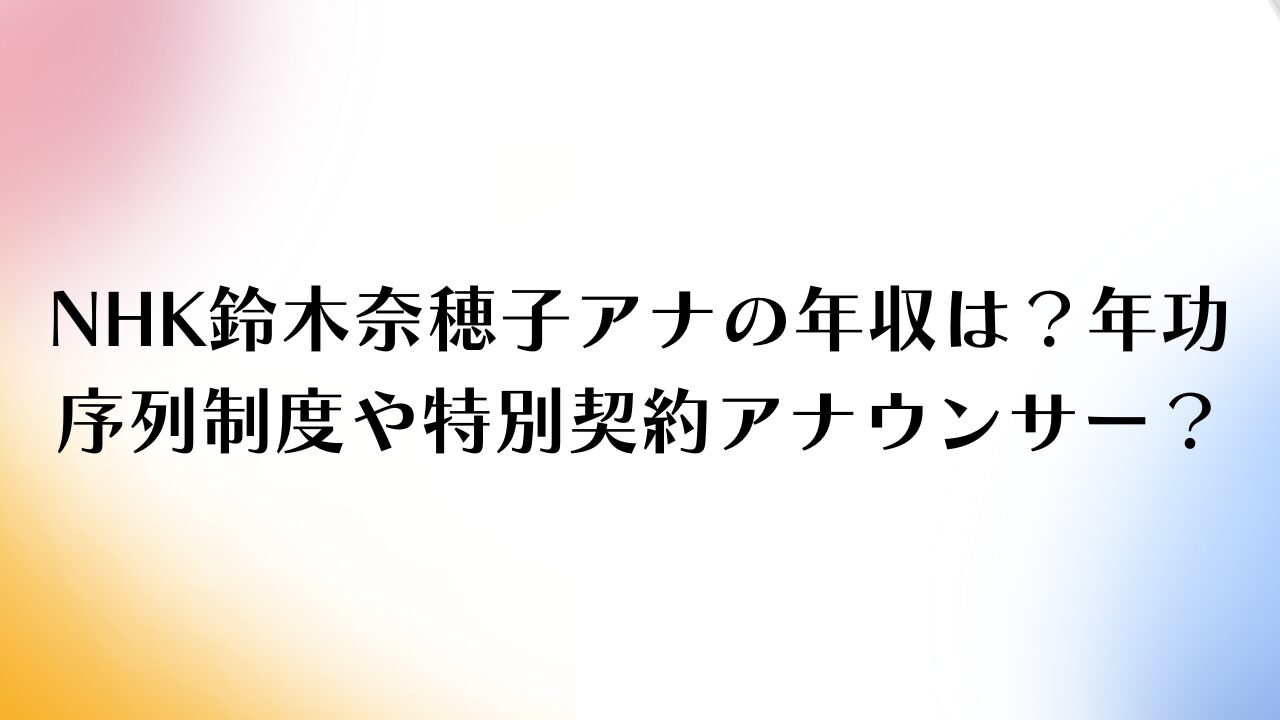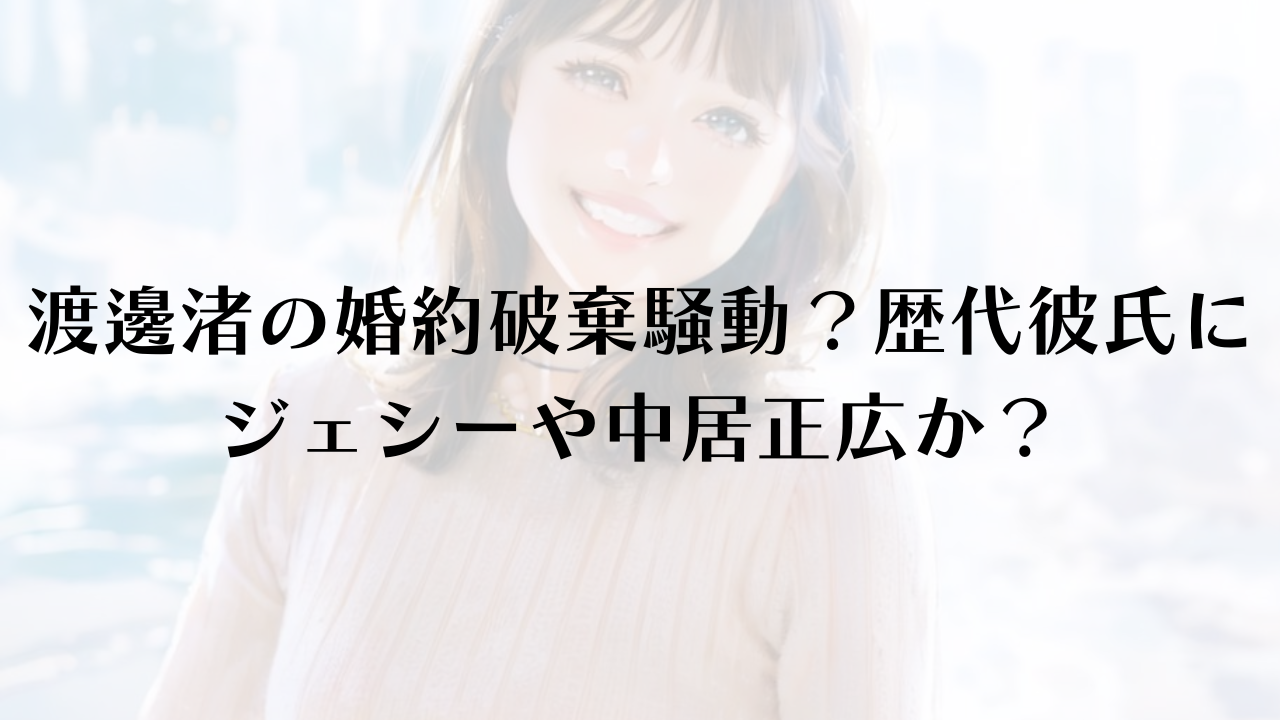日枝久による乗っ取り!創業者ら鹿内家を排除して帝国を築く!
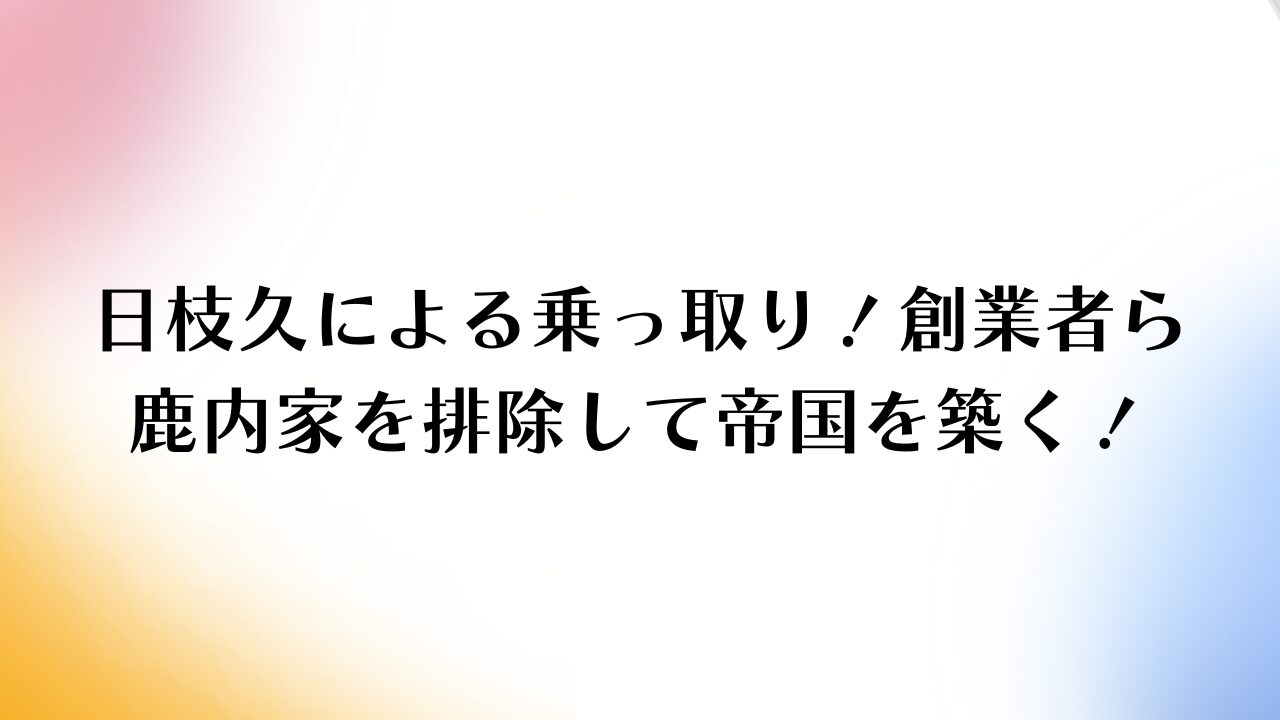
フジテレビの歴史において、日枝久氏による経営権奪取は大きな転換点となりました。創業家の鹿内家から権力を掌握し、フジテレビを自らのビジョンで導いていった過程は、日本のメディア界に衝撃を与えました。
多くの人が「日枝久による乗っ取り」と呼ぶこの出来事は、単なる企業の内紛ではありません。それは、日本の放送業界全体に影響を及ぼす大きな変革でした。
本記事では、フジテレビの創業から日枝氏の台頭、そして経営権継承問題に至るまでの経緯を詳しく解説します。日枝氏がどのようにして影響力を拡大し、最終的にフジサンケイグループの構造を変えていったのか。その戦略と手法、そして結果としてもたらされた変化を多角的に分析していきます。
テレビ局の裏側で繰り広げられた権力闘争の実態に迫ります。書籍「二重らせん 欲望と喧噪のメディア」でもより詳細にまとめられています。
- 日枝久の経営権獲得の経緯
- フジテレビの組織改革の詳細
- 鹿内家との権力闘争の実態
- 日枝体制の功罪と長期影響
日枝久による乗っ取りの全貌
フジテレビの歴史において、日枝久氏による「乗っ取り」は大きな転換点となりました。創業家である鹿内家から経営権を奪取し、フジテレビを自らの思い描く方向へと導いていった過程は、日本のメディア界に大きな衝撃を与えました。
ここでは、フジテレビの創業から日枝氏の台頭、そして経営権継承問題に至るまでの経緯を詳しく見ていきます。日枝氏がどのようにして影響力を拡大し、最終的にフジサンケイグループの構造を変えていったのかを探ります。
フジテレビの創業と鹿内家
フジテレビの誕生は、日本のメディア界に大きな影響を与えました。1957年、鹿内信隆氏を中心とする経営陣によって株式会社富士テレビジョンが設立されました。鹿内家は、この新しい放送局の中心的存在として、その後の発展に大きく貢献することになります。
当初、フジテレビは東京都内の一角に小さなスタジオを構えるだけでしたが、鹿内信隆氏の先見性と経営手腕により、急速に成長していきました。特筆すべきは、鹿内氏が「娯楽性と情報性の融合」という新しい放送スタイルを提唱したことです。これは、後のフジテレビの特徴となる「楽しくて、ためになる」番組作りの基礎となりました。
鹿内家は、単なる経営者としてだけでなく、番組制作にも積極的に関与しました。例えば、鹿内信隆氏は、人気番組「欽ちゃんのどこまでやるの!」の企画段階から参加し、その斬新な内容に太鼓判を押したといいます。
このように、フジテレビの創業期において、鹿内家は経営と制作の両面でリーダーシップを発揮し、新興放送局を業界の一大勢力へと成長させる原動力となったのです。
日枝久のフジテレビ入社
1961年、フジテレビに一人の若者が入社しました。その名は日枝久。彼の入社は、後にフジテレビの歴史を大きく変える出来事となりました。
日枝は、当初は目立たない存在でした。しかし、彼の独特の発想力と行動力は、徐々に周囲の注目を集めるようになります。例えば、入社後まもなく、彼は社内の労働組合結成に奔走しました。これは、単なる労働環境の改善だけでなく、社員の意識改革にもつながる重要な取り組みでした。
また、日枝は番組制作にも積極的に関わりました。彼は、「視聴者が何を求めているか」を常に考え、斬新なアイデアを次々と提案しました。この姿勢は、上司たちの目にも留まり、彼の昇進につながっていきます。
さらに、日枝は経営面でも才能を発揮しました。彼は、放送業界の将来を見据え、デジタル化やグローバル化への対応の必要性を早くから主張していました。この先見性は、後にフジテレビの経営戦略に大きな影響を与えることになります。
このように、日枝のフジテレビ入社は、単なる一社員の採用にとどまらず、後の放送業界に大きな影響を与える人物の登場を意味していたのです。
視聴率向上と日枝の台頭
1980年代、フジテレビは大きな転換期を迎えます。その中心にいたのが、日枝久でした。彼は、42歳という若さで編成局長に抜擢され、フジテレビの番組編成に大きな変革をもたらしました。
日枝の戦略は明確でした。「視聴者が求めるものを、求める時間に提供する」というシンプルな方針です。しかし、その実行は革新的でした。例えば、それまでの常識を覆し、ゴールデンタイムにバラエティ番組を集中させるという大胆な編成を行いました。
この戦略は見事に的中し、フジテレビの視聴率は急上昇します。「オレたちひょうきん族」や「夕やけニャンニャン」といった番組が大ヒットし、フジテレビは「お茶の間の人気者」となりました。
さらに、日枝は新しい才能の発掘にも力を入れました。若手芸人や新人ディレクターに積極的にチャンスを与え、新鮮な番組作りを推進しました。この姿勢は、フジテレビに新たな創造性をもたらしました。
こうした成功により、日枝の社内での影響力は急速に拡大していきます。彼は単なる編成のプロフェッショナルから、フジテレビの未来を担う経営者としての地位を確立していったのです。
鹿内家の経営権継承問題
1988年、フジテレビは大きな転換点を迎えます。創業者の鹿内信隆氏の長男である春雄氏が突然他界したのです。これにより、鹿内家の経営権継承問題が浮上しました。
当初、後継者として有力視されていたのは、鹿内信隆氏の次女の夫である佐藤宏明氏でした。佐藤氏は鹿内家に養子として迎えられ、鹿内宏明と名を改めました。彼は、フジサンケイグループの議長代行として、すでに経営に携わっていました。
しかし、この継承劇は思わぬ展開を見せます。鹿内宏明氏のワンマン経営スタイルが、社内外で批判を浴びるようになったのです。特に、フジテレビの成長を支えてきた日枝久らとの軋轢が表面化しました。
この状況下で、1992年に大きな転機が訪れます。フジテレビ社長の日枝久氏や産経新聞社社長の羽佐間重彰氏らが中心となり、鹿内宏明氏の解任を目的とした「クーデター」が起こったのです。
結果として、鹿内宏明氏はグループ内の主要ポストから退くことになりました。これにより、創業家による直接的な経営支配は実質的に終焉を迎えることになったのです。
この出来事は、フジテレビの歴史において重要な転換点となりました。創業家の支配から離れ、新たな経営体制を構築する道が開かれたのです。
日枝久の組織内での影響力拡大
鹿内家の経営権継承問題を経て、日枝久の影響力は急速に拡大していきます。1988年にフジテレビの社長に就任した日枝は、その手腕を遺憾なく発揮し始めました。
日枝の経営スタイルは、「攻めの経営」として知られるようになります。彼は、テレビ局の枠を超えた事業展開を積極的に推進しました。例えば、映画製作への本格参入や、音楽事業の強化などです。これらの新規事業は、フジテレビの収益基盤を大きく拡大させることになりました。
また、日枝は人材育成にも力を入れました。彼は、若手社員に大きな権限を与え、新しいアイデアを積極的に採用しました。この方針により、フジテレビは常に新しい風を取り入れ、時代の先端を走り続けることができました。
さらに、日枝はグループ全体の統括にも乗り出します。フジサンケイグループ内での発言力を強め、グループ全体の戦略立案に深く関与するようになりました。この過程で、彼はグループ内の各社の連携を強化し、シナジー効果を高めることに成功しました。
こうして、日枝はフジテレビ一社の経営者から、メディアコングロマリットの指導者へと成長していきました。彼の影響力は、もはやテレビ業界だけにとどまらない、日本のメディア界全体に及ぶものとなったのです。
フジサンケイグループの構造変化
日枝久の影響力拡大に伴い、フジサンケイグループの構造にも大きな変化が訪れます。2008年、グループは大きな組織改編を行い、認定放送持株会社制度を導入しました。
この改編により、フジテレビジョンは株式会社フジ・メディア・ホールディングス(FMH)に社名を変更し、グループの中核企業となりました。FMHは、フジテレビやニッポン放送、産経新聞社など、グループ内の主要企業を傘下に収めることになったのです。
この新体制の狙いは明確でした。それは、グループ全体の経営効率を高め、急速に変化するメディア環境に柔軟に対応することでした。例えば、テレビ、ラジオ、新聞といった従来のメディアと、インターネットなどの新しいメディアとの融合を促進することが可能になりました。
また、この構造変化により、日枝久の影響力はさらに強固なものとなりました。彼はFMHの会長兼CEOに就任し、名実ともにグループ全体の舵取り役となったのです。
しかし、この新体制には課題もありました。グループ内の各社の独立性をどう保つか、また、急速な技術革新にどう対応していくかなど、新たな問題に直面することになったのです。
このように、フジサンケイグループの構造変化は、日本のメディア業界に大きな影響を与えると同時に、グループ自体にも新たな挑戦をもたらすことになりました。
フジテレビ乗っ取りと日枝久の戦略
日枝久氏によるフジテレビの「乗っ取り」は、緻密に計画された戦略的な動きでした。この章では、日枝氏がどのように社内クーデターを実行し、鹿内宏明氏を解任に追い込んだのかを詳しく見ていきます。
また、持株会社体制への移行やライブドア買収騒動への対応など、日枝氏が直面した様々な課題とその対処法を探ります。
さらに、日枝体制の確立とそれに対する批判、そして長期にわたる支配と影響力についても考察します。日枝氏の戦略がフジテレビにもたらした変化と影響を多角的に分析していきます。
社内クーデターの実行
1992年、フジテレビ内部で大きな転換点となる出来事が起こりました。当時のフジサンケイグループ議長だった鹿内宏明氏を追放する社内クーデターが実行されたのです。
このクーデターの中心人物は、フジテレビ社長の日枝久氏でした。日枝氏は、産経新聞社社長の羽佐間重彰氏らと手を組み、緻密な計画を立てて行動しました。
クーデターの背景には、鹿内氏のワンマン経営に対する不満がありました。グループ内での権力争いや経営方針の対立が、この事態を引き起こしたのです。
日枝氏らは、まず産経新聞社の取締役会で鹿内氏の会長職解任を決議しました。その後、ニッポン放送やフジテレビでも同様の動きが続き、鹿内氏は次々と要職から追われていきました。
このクーデターの成功により、フジサンケイグループの経営体制は大きく変わりました。創業家である鹿内家の影響力が一掃され、日枝氏を中心とする新たな経営陣が実権を握ることになったのです。
この出来事は、日本のメディア業界に大きな衝撃を与えました。長年続いた創業家支配の終焉と、新たな経営体制の誕生を象徴する出来事として、今でも語り継がれています。
鹿内宏明の解任劇
1992年7月21日、フジサンケイグループに激震が走りました。グループ議長だった鹿内宏明氏が、突如として産経新聞社の取締役会で会長職を解任されたのです。
この解任劇は、前述の社内クーデターの集大成とも言える出来事でした。鹿内氏は「グループを私物化し、新聞を代表する者として不適任である」という理由で解任されました。
実は、鹿内氏はこの事態を予測していたようです。同年6月のフジテレビ株主総会では、自身の解任の噂が流れていました。しかし、鹿内氏の強硬な人事策は、かえって反対派の結束を強めることになってしまいました。
解任後、鹿内氏は孤立無援の状態に陥りました。大株主だった創業者の未亡人からも見放され、支持基盤を失ってしまったのです。
翌日の7月22日、鹿内氏は記者会見を開き、ニッポン放送、フジテレビジョン、サンケイビルの会長職とフジサンケイグループ議長を辞任すると発表しました。この会見は、フジテレビ第5スタジオで行われ、多くのメディアが詰めかけました。
この解任劇により、鹿内家のグループ経営支配は終焉を迎えました。長年続いた創業家による経営体制が崩壊し、新たな時代の幕開けとなったのです。
持株会社体制への移行
2008年、フジテレビは大きな組織改革を行いました。それは、放送持株会社制度への移行です。この改革により、フジテレビジョンは株式会社フジ・メディア・ホールディングス(FMH)に社名を変更し、グループの中核企業となりました。
この新体制の目的は、急速に変化するメディア環境に柔軟に対応し、グループ全体の経営効率を高めることでした。FMHは、フジテレビやニッポン放送、産経新聞社など、グループ内の主要企業を傘下に収めることになりました。
持株会社体制への移行には、いくつかの利点がありました。まず、グループ全体の資金調達が容易になりました。これにより、デジタル化に伴う大規模な設備投資にも対応できるようになったのです。
また、テレビ、ラジオ、新聞といった従来のメディアと、インターネットなどの新しいメディアとの融合も促進されました。この体制により、メディア間の垣根を越えた新たなサービスの開発が可能になったのです。
しかし、この新体制には課題もありました。グループ内の各社の独立性をどう保つか、急速な技術革新にどう対応していくかなど、新たな問題に直面することになりました。
この持株会社体制への移行は、日枝久氏の影響力をさらに強固なものにしました。日枝氏はFMHの会長兼CEOに就任し、名実ともにグループ全体の舵取り役となったのです。
ライブドア買収騒動への対応
2005年、フジテレビは思わぬ危機に直面しました。インターネット企業のライブドアが、フジテレビの筆頭株主だったニッポン放送の株式を大量に取得したのです。これは、フジテレビの支配権を狙った敵対的買収の試みでした。
ライブドアの堀江貴文社長は、東京証券取引所の時間外取引を利用して、一気にニッポン放送の株式を29.5%取得しました。この手法は合法でしたが、その急速な買収プロセスに対して多くの懸念が広がりました。
フジテレビ側は、この事態に対して迅速に対応しました。まず、ニッポン放送が新株予約権をフジテレビに発行し、ライブドアの株式の価値を薄めようとしました。しかし、この策は裁判所によって差し止められてしまいました。
次に、フジテレビは他の企業と連携して対抗策を練りました。ソフトバンクやニッポン放送の株主である大株主たちと協力し、ライブドアに対抗する体制を整えたのです。
最終的に、この騒動は和解によって決着しました。ライブドアはニッポン放送の株式をフジテレビに譲渡し、その代わりにフジテレビがライブドアに出資することになりました。
この事件を通じて、フジテレビは企業防衛の重要性を再認識しました。また、メディア業界における企業買収の在り方にも一石を投じることになり、業界全体に大きな影響を与えたのです。
日枝体制の確立と批判
社内クーデターの成功とライブドア騒動を乗り越え、日枝久氏の体制は確固たるものとなりました。日枝氏は、フジテレビの社長から会長へと昇進し、さらにフジ・メディア・ホールディングスの会長兼CEOに就任。グループ全体の実質的なトップとしての地位を確立したのです。
日枝体制下でのフジテレビは、「攻めの経営」で知られるようになりました。テレビ局の枠を超えた事業展開を積極的に推進し、映画製作への本格参入や音楽事業の強化など、収益基盤の拡大に成功しました。
また、日枝氏は人材育成にも力を入れました。若手社員に大きな権限を与え、新しいアイデアを積極的に採用する方針を取りました。この姿勢により、フジテレビは常に新しい風を取り入れ、時代の先端を走り続けることができたのです。
しかし、その一方で日枝体制への批判の声も上がるようになりました。長期政権による経営の硬直化や、過度の権力集中による弊害を指摘する声が、社内外から聞かれるようになったのです。
特に、視聴率の低下や不祥事の発生など、フジテレビの問題が表面化するにつれ、日枝氏の経営手腕を疑問視する声も増えていきました。「フジテレビの天皇」と呼ばれた日枝氏の存在が、かえって組織の改革を妨げているのではないかという批判も出てきたのです。
このように、日枝体制は成功と批判の両面を併せ持つものとなり、フジテレビの将来に大きな影響を与え続けることになりました。
日枝久の長期支配と影響力
日枝久氏のフジサンケイグループにおける影響力は、実に37年もの長きにわたって続いています。1988年にフジテレビの社長に就任して以来、日枝氏はグループの実質的なトップとして君臨し続けてきました。
2017年、日枝氏は会長職を退きましたが、その影響力は衰えることはありませんでした。取締役相談役やフジサンケイグループ代表として、依然として強い発言力を持ち続けているのです。
日枝氏の長期支配の背景には、彼の卓越した経営手腕があります。1980年代のフジテレビの黄金期を牽引し、「フジテレビの天皇」とまで呼ばれた実績は、彼の影響力の源泉となっています。
しかし、この長期支配には批判の声も上がっています。「院政」と呼ばれるほどの影響力の行使は、組織の新陳代謝を妨げているのではないかという指摘もあります。実際、幹部人事や経営方針において、日枝氏の意向が色濃く反映されているとされています。
また、フジテレビの業績低迷や不祥事の際には、日枝氏の責任を問う声も上がっています。「視聴者ではなく、幹部が日枝氏を重視する姿勢が、フジテレビの低迷を招いている」という批判もあります。
一方で、日枝氏の支持者たちは、彼の経験と人脈がグループの安定に寄与していると主張します。メディア業界の激しい変化の中で、日枝氏の存在が重要な役割を果たしているという見方もあるのです。
このように、日枝久氏の長期支配と影響力は、フジサンケイグループの歴史そのものと言えるほど大きなものとなっています。その功罪両面が、今後のグループの行方を左右する重要な要素となっているのです。
まとめ:日枝久のフジテレビ乗っ取りについて
この記事を総括していきます。
- 日枝久の「乗っ取り」はフジテレビの歴史における大きな転換点
- 1957年、鹿内信隆氏を中心に株式会社富士テレビジョンが設立
- 鹿内家は「娯楽性と情報性の融合」という新しい放送スタイルを提唱
- 1961年、日枝久がフジテレビに入社
- 日枝は社内の労働組合結成に奔走し、番組制作にも積極的に関与
- 1980年代、42歳で編成局長に抜擢された日枝が番組編成に変革をもたらす
- 「オレたちひょうきん族」などのヒット番組で視聴率が急上昇
- 1988年、鹿内家の経営権継承問題が浮上
- 1992年、日枝らによる「クーデター」で鹿内宏明氏が解任される
- 日枝は「攻めの経営」で知られ、テレビ局の枠を超えた事業展開を推進
- 2008年、放送持株会社制度を導入しフジ・メディア・ホールディングスを設立
- 2005年、ライブドアによる敵対的買収の試みに対応
- 日枝体制下で映画製作や音楽事業など収益基盤を拡大
- 長期政権による経営の硬直化や権力集中への批判も存在
- 日枝は37年にわたりグループの実質的なトップとして影響力を維持
- 2017年に会長職を退いた後も、取締役相談役として強い発言力を保持
- 日枝の長期支配には功罪両面があり、グループの将来に大きな影響を与える
ここまで日枝久さんのフジテレビ「乗っ取り」劇について、かなり詳しく見てきましたね。正直、びっくりするような展開の連続でした。
テレビ局の裏側って、こんなにドラマチックなんですね。日枝さんの戦略的な動きや、鹿内家との権力闘争、そしてライブドア騒動まで。まるでサスペンスドラマを見ているような感覚でした。
個人的に面白いと思ったのは、日枝さんの長期政権。37年も君臨し続けるって、すごい影響力ですよね。でも、それが良かったのか悪かったのか、意見が分かれるところかもしれません。
結局のところ、日枝さんの「乗っ取り」は成功だったのでしょうか?それとも失敗だったのでしょうか?それは、見る人の立場によって変わってくるのかもしれませんね。
ただ一つ言えるのは、この「乗っ取り」劇が、フジテレビだけでなく、日本のメディア界全体に大きな影響を与えたということ。これからのテレビ業界がどう変わっていくのか、ますます目が離せなくなりそうです。
この乗っ取りの詳細なことは本にもなっているのでご興味ある方は一読されると良いですよ!よりフジテレビのゴタゴタが楽しめます(笑)

中居正広のトラブルをリークした人の正体や理由!複数の可能性を徹底検証
清水賢治(フジテレビ新社長)経歴アニメで功績!ドラゴンボールやちびまる子ちゃんなど
中居正広は推定年収5~10億円?全財産は100億円超えとの噂!
中居正広に渡邊渚は何された?野菜プレイや妊娠の噂?週刊誌のデマ報道箇所
フジテレビの何が問題で悪いのか?わかりやすく解説【中居正広の件】
渡邊渚の婚約破棄騒動?歴代彼氏にジェシーや中居正広か?結婚観を探る
のんびりなかい会員数は7万人以上か?驚きの料金設定でも月700万円超
港浩一(フジテレビ社長)は年収8200万円?フジテレビ社長の収入源を解説
フジテレビは潰れない!純資産9000億円弱で強固な財務基盤あり!
フジテレビの株価はなぜ上がる?業績不振の裏側や意外な強さの秘密
港浩一(フジテレビ社長)はカツラ説の真相に迫る!年齢を感じさせない髪型の謎